
——蓮井さんは高校を卒業されてロンドンに留学をされたんですね
高校を卒業して日本の大学に行ったんですが、1年で辞めてそこからロンドンに留学しました。
——ファッションを勉強するためですか
服飾より美術の方に興味があったのと、あとはちょっと日本から離れてみたいっていうのが気持ちとしてあったので。パリ、ロンドン、ニューヨークなど選択肢はあったと思うんですが、デザインする上でのプロセスを学ぶことが出来そうだったのでロンドンに決めました。チェルシー・カレッジ・オブ・アーツという美術大学に一年、その後セントラル・ セントマーチン美術大学に。チェルシーにいた時はドローイングしたり、絵を描いたり、スカルプチャーを作ったり、わりと抽象的な表現をすることが多かったですね。セントマーチンの時も、10秒でドローイングしたり、左手でドローイングしたり、感覚的な部分を養う授業がありました。面白いですよね。セントマーチンにはBA(大学)とMA(大学院)があるんですが、大学ではテキスタイル科でMAの時にファッション科の中のニットを選考しました。
——徐々にニットに惹かれていったのですね
BAの時にファッションウィークでコレクションを発表しているブランドにインターンに行きました。そこでニットのチームに入ったのですが、そのチームで一緒にもの作りができたのがとても楽しかったんです。いろんな国籍の人がいて、いろんな考え方をして、とてもいい刺激を受けたのがニットを好きになるきっかけになったのかもしれません。
——まだその時はブランドを立ち上げるとことは考えていなかったのですか
ロンドンって写真家やスタイリスト、ヘアメイクなど個人でフリーとして活動する人が多く、学生もそうだったんです。 自分でポートフォリオを作って、いろんなところにアプローチをして。そういうことが普通にある環境だったので、私も毎年ポートフォリオを作ってブランドに持って行きました。
なので、ブランドをスタートさせるというよりは自分のポートフォリオを更新していくという作業が、その後のブランドの立ち上げの基礎になったのだと思います。

——日本に帰ってきてブランドを立ち上げる時はどんなようなタイミングでしたか
JFWのコンペがあって、ポートフォリオを送って最終決定したことがブランドの立ち上げでした。実は日本に帰ってきてから一年半ぐらいメンズのブランドの「アトウ」で働いていたのですが、ちょうど辞めた後に自分の身の振り方でいろいろ考えていたタイミングでした。
——デビューコレクションの思い出は
あの頃はブランドをスタートさせた人が結構周りにいたんです。ある意味恵まれていたのかなと思います。一つのブランドでその時のファッションの流れを作るより、デザインの方向性は違っても同じ世代のパワーがファッションの流れを作っていたので。そういうことはとても重要なのだなと考えさせられました。
——デビューしてから15年、節目の時のショーでしたね
ショーでコレクションを発表しているブランドを多く経験したので、その楽しさやその場の空気感が好きなところはありました。
ただ、サイクルが早い中で毎回ショーをやるには規模的に難しいところがあるのと、あと自分自身写真がとても好きで、作ったものを写真で表現するというプロセスが好きなので、そういう意味ではショーではなくて毎回写真で見せるっていうことにとても興味がありました。
——表現方法はいろいろですね。今回の秋冬コレクションはどのようなテーマのもとにどのような表現をされたのですか?
ショー開催の一年ぐらい前から構想は練っていて、秋冬に関して言うと、昔から好きだったトレイシー・エミンの絵からインスピレーションを得ました。トレイシーの絵は女の人のドローイングで、途中から色が入り、最後にはもとの絵が見えないくらい崩されるという作風なんです。女性らしさをすごく感じるなと思って。服って服単体のプロダクトとして魅力はあるんですけど、そこからどう全体のバランスを崩すかが私にとっての課題でした。レースとかアンゴラとかファーとか、歴史的に女性らしさを表現するために使われていた素材を、クラシックにならないように崩しながらどう入れ込んでいくかというところをテーマにしました。
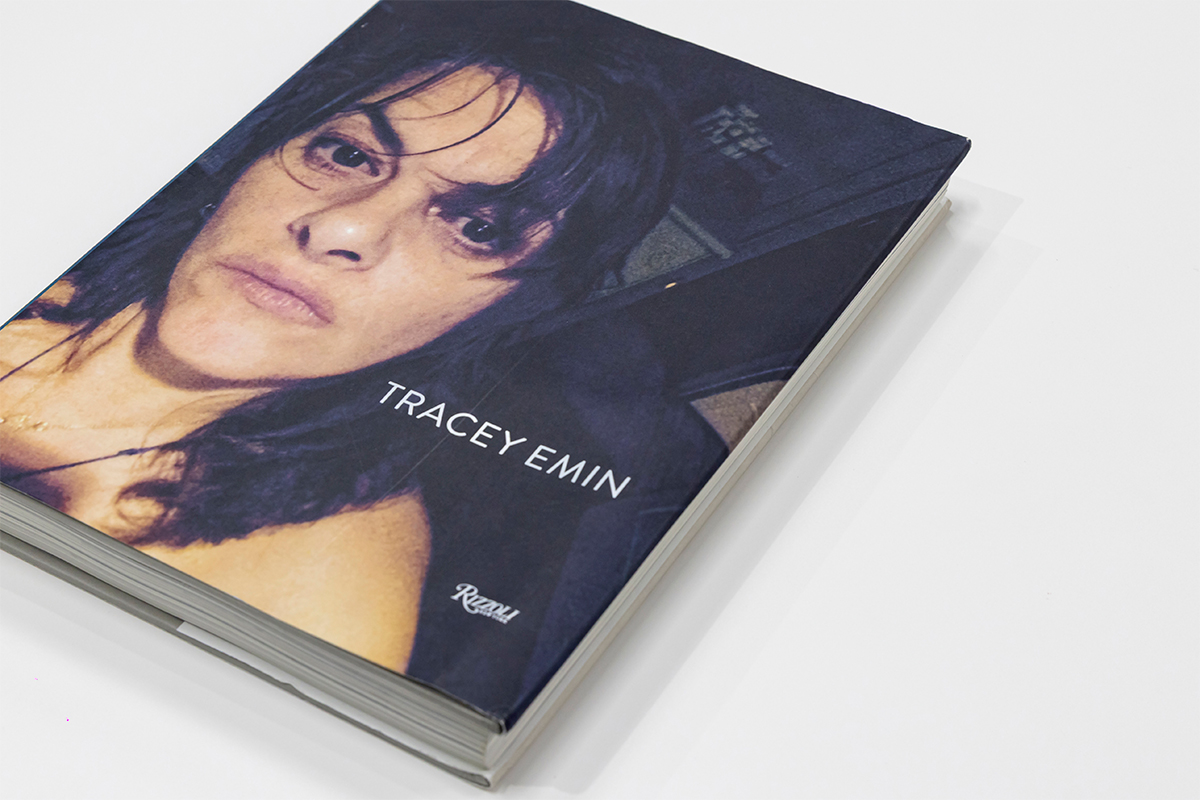
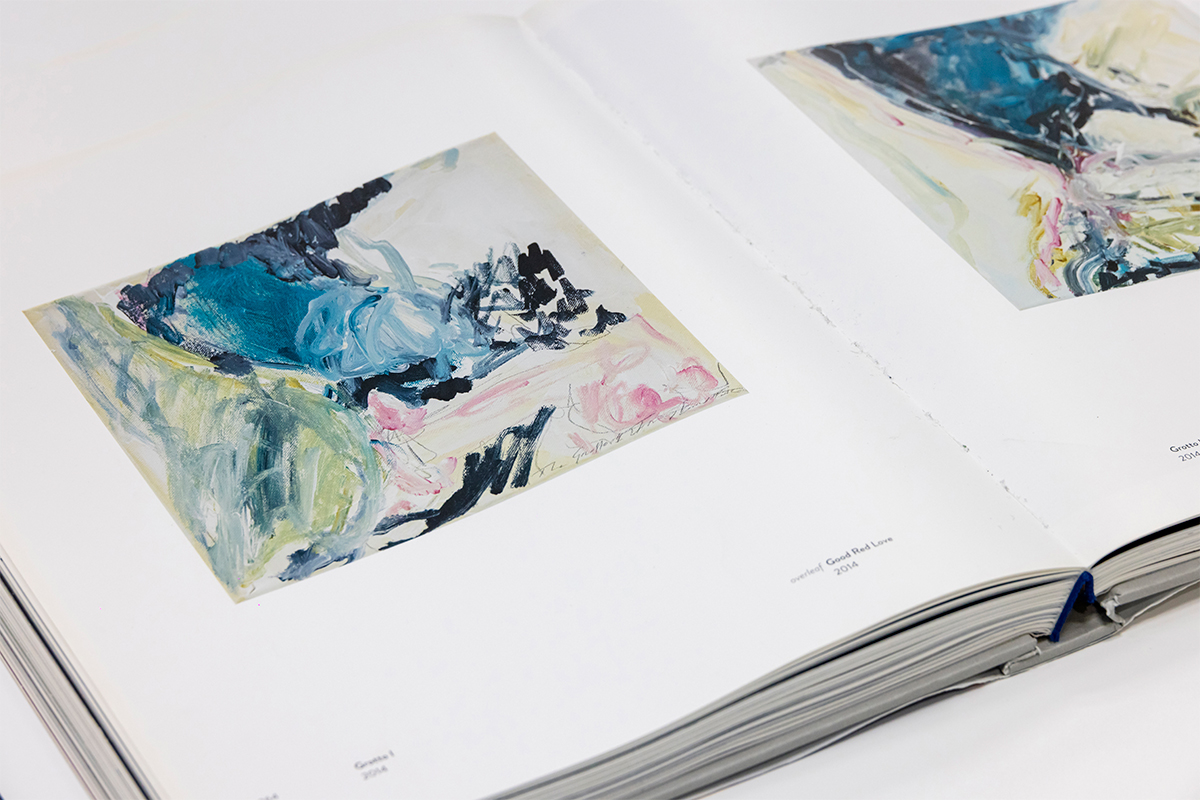
トレイシー・エミンの画集
——そこには具体的な女性像みたいなものはあったのですか?
それは良く聞かれるのですが、一度も想像したことがないんです。服に落とし込む時に、年齢とか、こういうタイプの人とかは考えることはありますが、全体を考える時に誰か特定の人はいうのはないですね。
——秋冬のコレクションの中から特徴的なところなど、打ち出したかったものを具体的に教えてください
ボリューム感とか素材感というのは、ニットだと優しい雰囲気になりがちなので、そういう意味ではさまざまな素材をレザーと合わせたり、スポーティな素材をミックスしたりしました。あとはブランドスタート時から体にフィットしたものや、露出のあるデザインを取り入れていたので、15年経ったところでそれをどういう風に表現するかっていうのは考えました。ボディースーツみたいなアイテムにコーデュロイのパンツをコーディネートしたり、カットしたニットのインナーにブラを見せるように合わせたり。


——ボリュームのバランスが絶妙でした
オープニングのドレスはレースやチュールの黒いドレスにニーハイのワークブーツ、そして大きなニット帽。崩しながらバランスを楽しむというのが大きなテーマでした。あとはスタイリングとキャスティングも、この人がこれを着たら面白いかもと。モデル一人一人の個性を生かしたスタイリングを試みました。
——スタイリングも蓮井さんが
自分でスタイリングをする時もありますが、今回のショーに関しては、スタイリストのデミデムさんにお願いしています。ニットをさらっと肩からかけたり、頭に巻いたり。ちょっと仕草的なところも意識しましたね。
あと大きなテーマとしてはカラーリングもそうです。 今までとはちょっと違うアプローチをした部分もあって、全体でのまとまりは保ちつつ単体でちょっと遊んでいるようなところもポイント。ファーストルックは黒っぽい感じから始まって、色を挟んで最後黒で終わるというような。ニットの捉え方としてはわりとベーシックなアイテムなんですが、遊びを持たせた着こなしが多いですね。
——展示会で見るとそれがよく分かります。一つ一つ普通に着られるアイテムなのにコレクションでの表現が素敵でした
服のイメージをどうやってお客さんに届けるかみたいなところが大事なところだと思います。

——蓮井さんがファッションを通して伝えたいことってなんでしょうか
ファッションに限らず、今はすぐ答えを出すようなことが求められたりしますよね。自分自身の意見が一方方向だったりもするし。そういうことではないところでの楽しさみたいなのが伝わるといいなと思います。私自身手を動かすことが好きなので、そういうことは常に思います。
——1つのものを探して答えを出すのにすごく時間がかかってでも、寄り道することで新たな発見があったりしますね
そうですね。学生時代、MAの時に課題でデザイナーのリサーチをすることがありました。そのデザイナーが過去に作ったものとか、いろんな本を調べてリサーチするんです。例えば、デザインのもとになったものを探したりするんですが、こういう流れがあるということを理解するのとしないのとでは、学ぶことの楽しみ方がちょっと違うのかなって思うんです。服を作るのって結構ローテクなことが多いんですよね。 素材一つとっても、そのデザインに合っているかどうかとか。デザインが面白くてきちんとできているものって、結構人の手がかかっているんです。
——先ほど学生時代にデザイナーについていろいろと調べていたと伺いましたが、調べていて影響を受けたデザイナーはいますか
その時はデザイナーのリサーチという課題で3人のデザイナーを選びました。私は、アズディン・アライアとヘルムート・ラングと山本耀司さん。その時にいろいろ調べたことがあってなのか、今ヨウジさん出身の方にパターンを引いてもらっています。今も学ぶことは多いですね。アライアについても、彼はトワルに向かってピンとハサミを使ってシルエットを出していたので、私が手を動かすのが好きなのはその影響かもしれないです。

——ファッションで少し違う分野のことをやりたいと思いますか
靴を作り始めたのは自分の中ではそういうことなのだと思います。服とはまた作る工程が違うので、職人さんとのやり取りの中で勉強しなければいけないことが多いです。でも、靴って重要ですよね。そのルックの雰囲気やブランド感は、どんな靴を合わせるかでイメージが変わりますから。時代感ともそうですね。
——毎シーズン撮影しているルックは写真家のご主人、蓮井元彦さんが撮影しているんですね
プライベートではあんまり仕事の話はしないですけど、ルック写真を毎回撮ってもらっているので、今はこういうのが面白いとか、こういうことに興味があるとかっていう話はお互いにしますね。職種が違うのでいろいろと話しやすい存在です。気がつくと正解がないものをずっと話していたり。お互いこうしなきゃいけないとか、こう働かなければいけないとかの縛りがないので、そういう意味では安心感はあります。
——今日、いつもお使いになっているスケッチブックをもってきていただいていますが
コレクションに取りかかるときは、部屋の壁にそのシーズンのボードを作ってイメージビジュアルみたいなものをランダムに貼るんです。ピンクのコレクションをやりたいとなったら、絵的に面白いピンクのものをたくさん貼って。ピンクの中に何色を入れるかとか、どういう風にしたらピンクが可愛すぎないかとか。それをなんとなく毎日眺めながらスタートするんですけど、このスケッチブックにはボードを見ながら絵や文字を書いたり、パタンナーに渡すための設計図みたいなものなど、忘れないようにあらゆることを書きとめています。

コレクションのアイディアが詰まったスケッチブック
——大変な作業ですね。
好きなので。
——好きなことを仕事にできているってすごく素晴らしいですね。
そうですね。だから、作れる環境をキープできるようにいろいろ試行錯誤して進んでいきます。
——蓮井さんからデザイナーを目指す人にエールをお願いします
ものを作るって不条理なこともあるので、それを早い段階で知っていた方がいいとは思うんですけど、それが多分昔はインターン制度だったと思うんです。今はインターン制度が少なくなっているかもしれないですが、そういう不条理さを勉強できる場所があるのはすごく大事かなと。あと、この世界あまり正解ってないことが多いので、答えを決めずにたくさん作ること。自分の時間を自由に使えるのは学生の強みだと思うので、いろいろたくさん作ってみることは大切ですね。
——今後の展望は
続けていくことです。今年で15周年。ブランドを始めた時は10年続けるのが目標で、10周年の時にはショーを発表しようと思ったんですけど、コロナ禍で諦めて。5年経った今回ショーをやりました。ショーをやるとなると、構成など違う角度でものを考えなければいけないですよね。物を売るということとは別に雰囲気を見せるから。でもこの先長く続ける中で、きっといろんな正解が待ち続けているから、そのときの気持ちやクリエーションによってベストな方法での発表を考えてみたいと思います。
photographs: Josui Yasuda(B.P.B.)
Akane Hasui
1982年東京生まれ。高校卒業後、渡英。セントラル・ セントマーチン美術大学卒業。帰国後、アパレルブランドを経て、2009年に「AKANE UTSUNOMIYA(アカネ ウツノミヤ)」を立ち上げる。ブランドコンセプトであるラグジュアリー、素材の特質、クリエーティブをもとに、ニットに特化した服作りを目指す。
WEB:http://www.akane-utsunomiya.com/
Instagram:@akaneutsunomiya














