日本から世界へ飛び出したクリエイターたちをシリーズで紹介。
今回のゲストはフランス料理のシェフ、小林圭さんです。

厨房に立つ小林 圭シェフ。店のスペシャリテ「庭園風季節のサラダ」を撮影のために盛り付け中。
「この仕事は苦しいだけ。でも喜びがある」
2020年1月、ガストロノミー界最高ランクの各付けが発表される会場に「ケイ・コバヤシ」の名前が響き渡った。沸き起こる歓声とスタンディングオーベーションに背中を押されながら、ステージに上がったのは日本人の小林 圭シェフである。フランス版ミシュランガイドでアジア人が初めて三つ星に輝いた瞬間だった。
「フランスを誇りに思います。あなたたちが外国人の僕たちを受け入れ、居場所を与えてくれたお陰です。ありがとう、フランス」
料理界の名だたるシェフたちを前に、しっかりとした口調でスピーチをした小林シェフ。そして誰よりも惜しみない拍手を送ったのは彼らだった。ここまでの道のりがいかに厳しいものかを身をもって知っているからだ。


2020年フランス版ミシュランガイドのセレモニーにて。
セレモニー直後のインタビューでは「 “嬉しい”ではなく、むしろホッとしている」と心情を吐露。
「ミシュランの重圧はすごいので。この仕事をしていて楽しいとは思いません。苦しいだけです。でも喜びがあるんですよ。お客さんが『おいしい』と言ってくださるのが嬉しい。三つ星を取ったから終わりではなくて、今からが始まりです。来年は四つ星ができるかもしれないですよね。ともかく上を目指していくしかありません」
「この道に入ったのは、シェフの制服がカッコよかったから」
長野県諏訪市出身の小林は、山と湖に囲まれた田舎町で育った。両親は共に料理人で、記憶に残る家庭料理は母親が作った煮物。祖父は兼業農家で、採れたての野菜の味と香りを今でも覚えている。毎年、田植えと稲刈りを手伝い、遊びといえば野球。家では兄と料理を作ることもあったそうだが、意外にも偏食だった過去があり、魚は小学校低学年まで、肉は中学年まで食べられなかったという。
料理人になると決めたのは15歳の時。両親に影響されたわけでもフランス料理が好きだったわけでもない。テレビで見たシェフのアラン・シャペルが着ていた制服に強く惹かれたからである。
「田舎でしたからフランス料理なんて食べたこともありませんでした。この道に入ったのは、これ(自分の服を指し)が理由です。白いシェフのジャケットがカッコよかったからなんです」

小林 圭シェフ。レストラン「KEI」にて。
地元にある会員制ホテルのレストランでサービス係の募集があることを知り、早速、面接に行った小林は、支配人に厨房で働きたいと交渉。この時、たまたま通りかかったのが、その後の人生に大きな影響を与えることになる中村徳宏シェフだった。
「中村シェフに専門学校へ行きながら厨房で働きたいと話しましたが、断られました。そして4つの条件を出されて、全部できるのであれば3日後に電話をしてくるようにと言われたんです」
その条件とは「ファーストフードを食べない」「親しい友だちと一度縁を切る」「彼女を作らない」「スキー、スノーボードをしない」である。
「次の日に『やりたい』と電話したら、早すぎると断られて、そんなに簡単に人生は決まらない、ちゃんと3日間考えるようにと言われました。だから3日間考えてから返事をしたんです。今になると、なぜシェフがそんなことを言ったかがわかります。その厨房では、一日18時間くらい働いていましたが、まわりの友だちはみんな学生で自由になる時間があります。一緒にいたら逃げ出したくなる可能性が増えますからね」
「もっと知りたい、自分の目で見てみたい」
小林はこの頃の自分を振り返り「危ないとわかっていても山のてっぺんからスキーで滑るような子供だった」と話す。「両親に反対されることはありませんでした。昔から鉄砲玉って言われていて、一度言い出したら聞かないと知っていましたから」
こうして始まった下積み時代。フランス通で勉強熱心な中村シェフの下、料理への関心を深めていった小林は、本場のフランスへの思いを募らせていった。
「シェフからフランスの話を聞いて、もっと知りたい、自分の目で見てみたいと思うようになったんです。彼から学んだのは、料理だけではなく、人として生きていくための基礎でした。見て覚えろというやり方の厨房で、厳しかったですが、上の人間が何を思っていて何を必要としているのかも学びました。そこでの4年間と、シェフの勧めで働いた東京のレストランでの2年間は怒られっぱなしで、一生分怒られた感じです。そのお陰でフランスの厨房ではほとんど怒られたことがないんです」
「厨房に入ればどうにかなると信じていた」
待望の地、フランスに渡ったのは21歳の時。寒波に襲われた1998年の12月、「ともかく寒かった」というのが第一印象である。
「バスでパリに着きましたが、予約していたホテルが見つからず、大きなスーツケースを持って凱旋門のまわりを何周もしました。2時間以上歩きましたね。言葉がわからず、その時に話せたのは厨房で覚えた片言のフランス語だけでしたから。でも、365日の364日厨房に入っていたので、フランスでも厨房に入ればどうにかなると信じていたんです」
順調にいけば、パリに3日間滞在した後、地方のレストランで働く予定だった。
「話が通っていなくて、立ち往生したんです。持っていたお金が15万円くらいでしたが、最初のホテル代で4万円近く使ってしまったので、節約しながら過ごしました。日本のシェフの口利きで部屋を貸してもらえたのですが、何もすることがないので美術館に行って、地下鉄には乗らずにずっと歩いていましたね。でも段々お金が減っていって、結局1か月半パリにいましたが、3日間でバゲット1本を食べる生活をしていました。今でも覚えているのは、12月24日に1人で食べたケバブ(トルコ由来のラム肉入りサンドイッチ)です。フランスに来て最初のご馳走でしたから。日本に帰ったときには栄養失調になっていましたね」


厨房での小林シェフは真剣そのもの。ダイナミックでいて繊細な“庭園風”の盛り付けが見る見るうちに完成していく。
「本当に働けるのか賭けだった」
1か月間、アルバイトで資金を貯め、再びフランスへ渡った小林は、今度こそはと別のレストランで働き始める。だが、その店は2週間後に閉店。
「二つ星のレストランなのに、ありえないことなんです。でも、スーシェフ(副料理長)が前に勤めていた店に一緒に行かないかと誘ってくれました。彼の仕事をもっと見たかったので、行くことにしましたが、数日しか一緒に働いていない日本人をよく信じるなと思いましたね。それで、辞書を使いながら話を進めましたが、本当にその店で働けるのか最後まで不安で。他の誘いを断っていたので、賭けでした」
小林が移転した先は、ラングドック地方にある二つ星(現在は三つ星)「オーベルジュ・デュ・ヴュー・ピュイ」である。シェフのジル・グジョンとは、今では誕生会に呼ばれるほどの仲だ。
「最初にジルから魚を担当するように言われましたが、魚はひと通り扱えるようになっていたので、フランスでは肉を勉強したくて、魚アレルギーがあると嘘を言って断ったんです。今では笑い話ですよ」
この時の小林はともかく仕事をした。朝8時から始めて終わるのは早くても夜中の2時。作業に追われて空腹でも休憩をとる時間さえなかった。
「一度だけ怒られたことがあるんです。ジルがアシスタントの失敗を僕の失敗だと思って『ケイ、出ていけ!』と怒鳴ったんです。『じゃあ出ていくよ』って、外に出たんですよね。『さあ、ここから何をしようか、今からパリに行こうかなぁ』って考えていたら、ジルがやって来て『料理をすべて止めてきた、ケイが戻らなければ出さない』って言ったんです。怒られたのはそれくらいですね」
「パリのトップのシェフの下で最後の仕上げをしたい」
フランス料理は様々な地方料理の集合体である。ゆえに、小林の当初の目的の一つは、地方をまわってその土地の料理を深く知ることだった。その計画を着々と実行した小林は、ラングドッグで働いた後、南フランス、アルザス、ブルターニュのレストランを経て、2003年からパリの「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」に籍を置く。料理界の重鎮、アラン・デュカスが監修するパラス・ホテルのレストランである。

錚々たるシェフたちの記念撮影。小林シェフ(中央)の右がアラン・デュカス氏。
「パリのトップのシェフの下で最後の仕上げをしたいと考えていました。だから地方にいた時から、今パリで誰が一番なのかリサーチしていました。それで、みんなが口を揃えて言ったのが、プラザ・アテネのジャン=フランソワ・ピエージュだったんです。だから、どんなことをしてもそこへ入りたいと思って、少しでも繋がりがある人にコンタクトしましたね。そうしないと入れない世界なんです。実際に入ってみたら、すべてが最高級のもので、やはり勉強になりました。プラザ・アテネという格式のある場所、アラン・デュカスの名前の三つ星、本当にいい食材も毎日集まってきます。30人の料理人、20人のサービス係、洗い場や事務の人がいて、全部で65人くらいいるんです。その人たちが対応するのは45人のお客さんです。だからこんなに完成度が高いんだと納得しました」
小林の最初のポストはコミ(下働き)のさらに下の2番手。そこから異例のスピードで昇進していき、2年でスーシェフになった。
「二つ星や三つ星のレストランから来た人でも最初は一番下からです。だから上の人間より下のほうが仕事ができることもありました。追い抜かれたら辞めるしかありません。競争率とライバル意識は強かったですね。自分の力をすべて見せないと使われる人間になってしまいます。僕は言葉では彼らに負けるんで、絶対に失敗してはいけないと思ってやっていました。デュカスさんのところではコンクールに出るのが禁止されていたので、休みの日にはマルシェ(市場)で材料を買って、一人でコンクールをしていましたね。例えばこの人参で何を作れるのかを考えて、そして3か月後に同じ課題を与えるんです」

「庭園風季節のサラダ」。ふんわりとしたロケットのムースを絡めて、様々なハーブの風味と食感が楽しめる。食べるのがもったいない!料理の写真は本誌でもお馴染みの蜷川実花さんが撮影。Photo by Mika Ninagawa
「自分の店を持つことは、職業を変えるようなもの」
実力と負けん気の強さを併せ持つ小林は、5年間スーシェフを務めた店をリーマンショックの折に辞めた。通常であれば保身にまわり、景気が戻るまで動かないものだが、次なる目標はシェフ(料理長)になること。一旦引くことで勝負に出たかったのだ。
まず始めたのは、フランス語の学校へ行くことだった。
「フランスのいいレストランでは、シェフがお客様のテーブルをまわって挨拶をします。厨房でずっとフランス語でしたが、だからといってきちんとした敬語が話せるわけではありません。だから半年間、まじめに語学学校へ通いました」
そして2011年、念願のシェフになると同時に自分の店「ケイ(KEI)」を持つことになる。
「ここを買った時に、前のオーナーシェフのジェラール・ベッソンさんから、自分の店を持つことは、職業を変えるようなものだと言われました。やってみて、1週間でわかりましたね。雇われシェフ時代とは違って、今は従業員のことを考えなければなりません。料理を考えることに費やせる時間は、30%あればいいほうです」
オープンから1年未満で一つ星を獲得した小林は、5年後に二つ星、さらにその3年後には栄誉ある三つ星を手中に収めた。

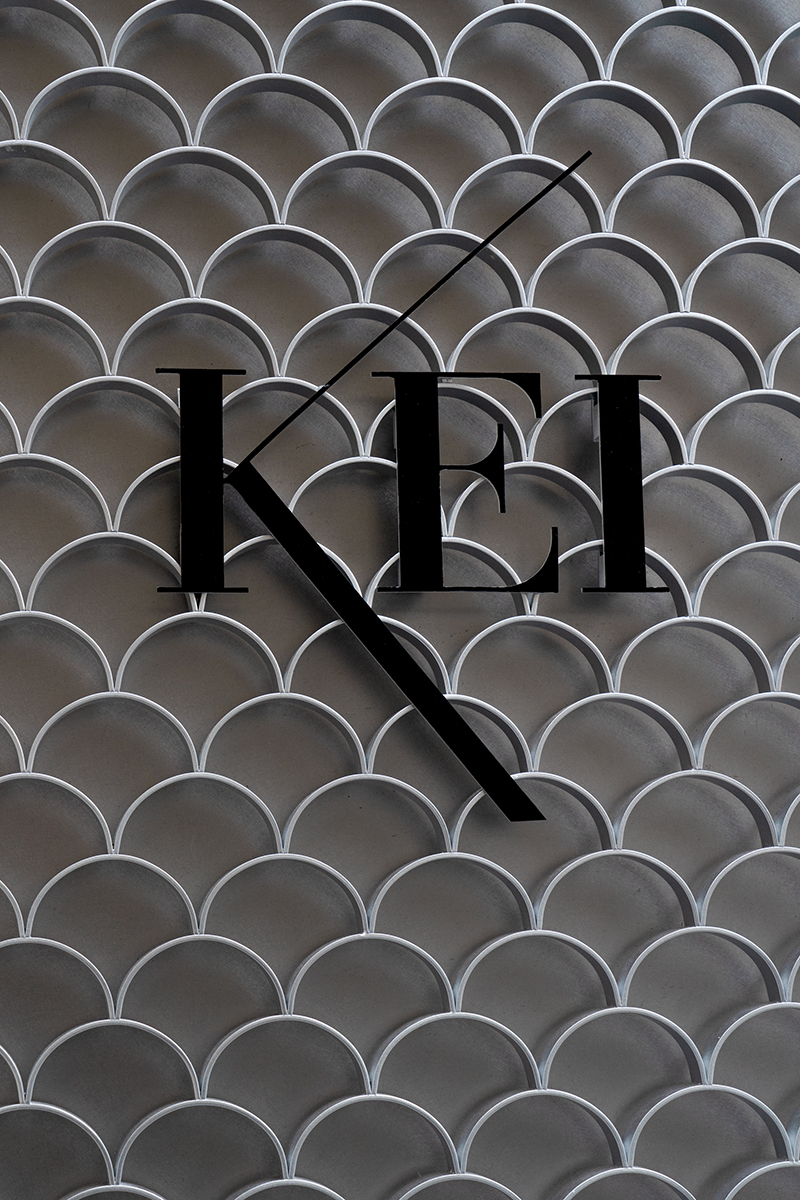

ルーブル美術館から徒歩数分の場所にあるレストラン「KEI」。昨年リニューアルオープンした店内は、格調の高さときらびやかな雰囲気を兼ね備えている。内装を手がけたのは建築家の田根剛さん。
NEXT:「取った命を皿に返して、お客さんの記憶に残るものにする」


