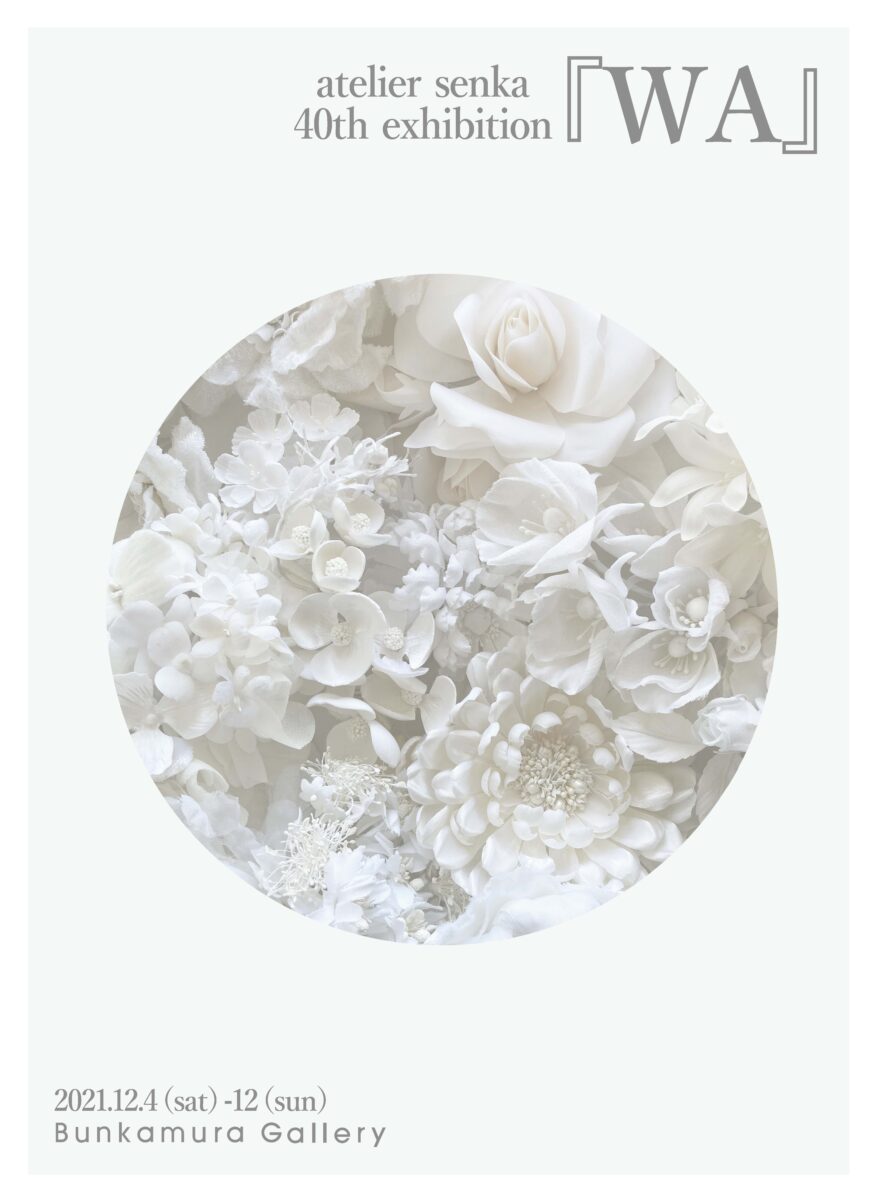「好き」や「夢」に対する向き合い方って人それぞれだし、正解は1つじゃない。
――映画『ドライブ・マイ・カー』のインタビュー(『装苑』2021年9月号)では、「自分が誰よりも役のことを知っている状態に持っていきたい」というお話をされていましたが、今回もやはり「共感」は演じるうえでの大きなポイントでしたか?
そうですね。好きであったものを仕事にしたがゆえに純粋に好きではいられなくなってしまった……ということは、この仕事に限らず、仕事に就いた経験がある全ての人が感じたことだと思います。特に表現の仕事は「好き」を入り口にする方が多いかと思うので、そういった悩みは非常にわかります。たとえば私にとって、歌うことは長い間趣味でした。でも、ご縁があってお仕事として歌わせていただいた前と後では、確実に違う何かがあるんです。その“何か”を言葉にすることはすごく難しいのですが、仕事にすることで何かが変わる、という感覚は私の中に明確にあります。
好きなものに執着するつらさといいますか、自分で自分の欲を感じて苦しくなるときって、あると思うんです。心ちゃんは映画の中で、一度、歌うことを好きでいるのをやめようとします。私は「好き」や「夢」に対する向き合い方って人それぞれだし、正解は1つじゃないと感じます。「好きでいるために、趣味にする」という方もいらっしゃいますし。最終的に、諦めても続けても、本人が納得しているならどちらも正解。ただ、せっかく好きになったものにふたをしてしまうのは、すごく悲しいことです。「自分はちゃんと好きだったな」と認められることが、大事だと感じます。私が一番彼女に共感できて、かつ、この映画を通して伝えたいなと思ったのは、「好きになった記憶を嫌なものにしない」という部分です。
――「好き」との向き合い方、非常に腑に落ちます。その仕事を選んだ理由が「好き」だったとしても、好き一辺倒だけではやっていけない瞬間も多いですよね。
そう思います。好きだけが唯一の正義や正解ではないとも感じますし、別に好きじゃないけど得意なことを仕事にしました、という人もいるかもしれない。私自身も、この仕事に対して「好きだからやっている」だけではない感情があります。ただ、好きが原因でできなくなってしまった、と自分が思ってしまうのはやっぱり寂しいとも思うんです。だからこそ、心ちゃんが「好きだったんだ、自分」と素直に言えるようなところにまで一緒にいけたらいいな、とは思っていました。

――三浦さんが脚本を精読するスタイルに辿り着いたのは、ご自身が衝撃を受けたという『台風クラブ』(1985年、相米慎二監督)の影響が大きいのでしょうか。
「本を読む」というところに直結して受けた影響とは少し違うのですが、確かにつながってはいます。というのも、『台風クラブ』を観るまでの自分は「ここで悲しい表情をして、ここでこういう動きをして、セリフはこういうニュアンスで……」と、頭の中でお芝居を計算していました。ですが、あの映画の中には自分の理解を超えた言い回しや、どこか動物的でゾクゾクする、いい意味で安心できない居方があって。それから、「自分が思いつくものを超えたい!」という欲が生まれたんです。
そのためには、もっと現場の空気をダイレクトに感じたり、これまで以上に共演者の表情や声に反応する必要がある。だったら、あんまり家で準備することをやめたほうがいいのかな?とも考えました。でも、準備をせずにその場に行くことがめちゃくちゃ不安で……(笑)。
何もしないで現場に行くことはやっぱり難しいので、逆に、どうしたら自分は自信を持って何もしない状態になれるんだろう?という考えにシフトしました。そのなかで「私はもう全部わかっています」という状態になれば自信が持てる、そのためにはとにかく本を読み込んで理解する、というやり方に辿り着いたんです。脚本をしっかり読み込んでちゃんと役のことをわかっているから、その場所に行って自然にふるまってもちゃんと役になる。そう安心して思えるための方法論でもありますね。

――そういう経緯だったのですね! 「人事を尽くして天命を待つ」ではないですが、役への深い理解があるからこそ、プラスアルファが開ける……。
それまでは「表現を決める」ための準備をしていたんですよね。そうじゃなくて、役をしっかり理解するための準備に時間を費やす。この先、お芝居をしていくうえでやり方は変わっていくかもしれませんが、いまの私が大事にしている考え方です。