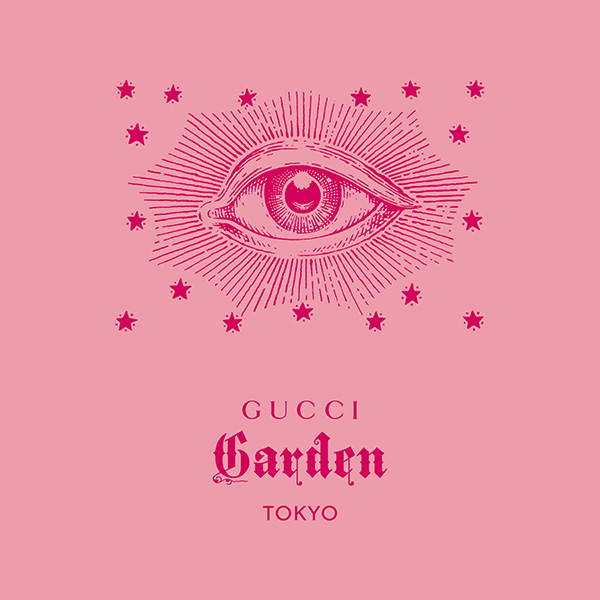これ以上ただ消費を煽り続けるメディアにしていくのか、もっと大切なことに気づき、集団として舵をきれるのか、その瀬戸際に今立っていると感じています。ーー池松壮亮

――あくまで個人的な意見ですが、いまの時代は作り手にとって健全なのか?と思うことがよくあります。というのも、受け手が一義的な正義のようなものを押し付ることがままあるので。そういった時代に、本作をテレビで放送することに非常に意義を感じますし、オダギリさんご自身も制作発表時のコメントで「賛否の大波紋を広げるであろう、世に『挑む』作品」とおっしゃっていましたよね。
オダギリ:僕がものづくりをする時には、いつも「良くも悪くも問題作であってほしい」と考えています。じゃないと作る意味がないとすら感じます。
確かにいまの世の中の受け取り方はちょっと過剰な点がありますが、賛否の“否”が多いなら、それはそれで嬉しい事なんですね。“賛”ばかりだとやっぱり、おかしな社会だと思うんですよ。「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」をみんなが絶賛する社会ってちょっと信じられないし(笑)、賛の人と否の人が意見を交わすことが、重要なんじゃないかなと。
ある作品に対して“否”ならば「なぜ自分は“否”と感じるのか?」をちゃんと考えて、自分に向き合うことこそ意味のあることですし、時代に関わらずものづくりというのはそういう機会を与えるものなんだと信じています。だからこそ、作る上ではやっぱり物議を起こさなくちゃいけないですよね。


「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」より
池松:すごくいい切り口でご質問くださったのでちゃんと答えたいんですが、そうした世の中に対する、オダギリさんなりの自覚的、あるいは無自覚的なカウンターだと僕は捉えています。
何かの時に、オダギリさんは「表現とはそもそもカウンターで、カウンターでなければ作っちゃいけない」といったようなことを話されていて、実にオダギリさんらしい言葉で感銘を受けました。「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」を全話観ていただければより伝わるかもしれませんが、この作品の奥底にはあらゆる精神が潜んでいると感じています。それは突き詰めると、オダギリさん自身の生きる美学のようなものだと言っても過言ではありません。
例えば脱成長。世界は資本主義という物語に毒され過ぎて息詰まっていますよね。映像業界も芸能界もその最たるものです。夢を与えることは大切なことですし、人にはそれぞれ役割があると思っていますが、これ以上ただ消費を煽り続けるメディアにしていくのか、もっと大切なことに気づき、集団として舵をきれるのか、その瀬戸際に今立っていると感じています。そしてオダギリさんという人の俳優活動や自身の作品からは、そこに対するカウンターのようなものを常々感じていました。同様に、この作品からはサボることの哲学のようなものも感じられます。サボると言っても何をサボるのかがとても重要なところですが、サボることも立派な意思であり、抵抗であると近頃よく思います。そんな様々な精神をはらみ、コロナで先が見えない混沌とした世界に、カオスをあえて作り上げるような、それでいて笑いという抵抗に包んでカオスを抱擁するような、そんな世界観を創り上げるのはまさにオダギリさんらしいと思いますし、全3話の随所にその意義が込められていると感じました。
この世界ではいつのまにか「期待に応えることや欲求を満たすこと」だけがエンターテインメントとされるようになってしまいましたが、オダギリさんは「驚かすこと」をエンターテインメントだと捉えているんじゃないかと思います。そしてこの作品では、後者を見てもらえると思います。
オダギリ:たとえば民放の深夜ドラマでこういうことをやるんじゃなく、あえてNHKで発表することが、いま池松くんが言ってくれたサプライズのひとつなんでしょうね。自分から一番遠いところにあるし、一番手を組まなさそうなんだけど、ここぞの勝負どころで組もうと思ったのは、僕自身が無難なところに『置きに行きたくない』という性質もあるんだと思います。「難しそう」だったり、「大変そう」なところに足を踏み入れたくなってしまう。俳優としてもそうですが、監督のときは特にそれが大きいかもしれません。

「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」より
――「シリーズ・横溝正史短編集」(’16年、’20年)や「あなたのそばで明日が笑う」(’20年)など、池松さんの近年の出演ドラマはNHK作品が多いですね。
池松:普段あまり多くテレビを見ていないのであれですが、近年NHKの2時間ドラマに気になる作品が多い気はしています。渡辺あやさんが脚本を手掛けた「ワンダーウォール」(’18年)には驚かされましたし、去年も何本か素晴らしいものに出会いました。
――個人的に、映画という表現に期待するもののすごく近くにNHKのドラマはあるような気がしますし、池松さんがおっしゃったことはまさにそうだと感じます。ある俳優さんにお話を聞いたときに「昔と違って、いまは視聴者が観たいものをドラマで描く時代になってきた」と語っていたのですが、NHK作品には新しいところに引っ張っていってくれる魅力を感じます。
池松:映画をやっていると、当たり前のように「何をいま語るべきなのか、後世に何を伝えるべきなのか、どうしたら映画で語るべき特別なものができるのか」を普段考えるのですが、NHKのドラマには同様の「何を語るか」という視点を感じます。
――本作は衣装などのビジュアル面も攻めていますよね。池松さんも着用されたハンドラーの衣装は、どのような経緯で生まれたのでしょう?
オダギリ:やっぱりこだわったものにしたかったんですよね。普段から、演じる役を考える時には髪型や衣装から入るんです。その人となりを視覚的に表現するものなので。今回もそれぞれのキャラクターに合うものを時間をかけて考え抜きました。
自分が若いときに観て、衣装も「格好いいな、真似してみたいな」と憧れるドラマってあったじゃないですか。僕自身もそういった作品に刺激をもらってきたし、せっかくならそういう作品を作りたい。「NHK WORLD-JAPAN」で展開されて海外で放送されることを想定して、日本のファッションや音楽、アートを格好良く詰め込んでいきたいとも考えていました。
池松くんにかぶってもらった赤いベレー帽も、日本の価値観ではあまり現実的ではないだろうけど、実際に海外の警察犬係にはいるんです。世界基準からしたらおかしな事ではない。リアリティを踏まえつつ、ファッションやアートな方向を選んでいましたね。



「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」より
――最後に、『装苑』の若い読者へのメッセージをお願いします。クリエイターを目指している方も多いので、きっと本作に大いに刺激を受けると思います。
オダギリ:『装苑』を読んでいる人たちはものづくりを目指す方々だと思いますし、つまりは同業者だと感じています。だからこそ、なかなか苦しい今の時期も諦めてほしくないですね。
皆それぞれ必ず才能があるし、ないというならそれはまだ発見できていないかもしれない。可能性は常にあります。だから、自分から諦めることはせずに、時間を忘れて没頭できるものをとことん掘り下げて、いきつくところまで極めてほしいですね。他者に合わせる必要はないし、世の中が何を求めているのかを探すよりも、自分が作りたいものをがむしゃらに突き詰めたほうがいいと思います。若い時は、『若気のいたり』こそが長所じゃないですか。ぜひ、わがままを突き詰めてください。そしていつか一緒に何かを作りましょう。
池松:僕もそう思います。あとは、世の中がいう「才能」ほど当てにならないものはないと思います。とりわけこの資本主義が行き過ぎた時代には。時代が勝手に決めて、大きなバランスの中で大多数になびいたものが「才能」と呼ばれるものです。スポーツの世界のようにルールが設定されて、結果がでるものではありません。狭い世界から反射させた価値基準を自分に向けるべきではないですし、それよりも、もっともっと自身の心の喜びのためにとことんやって欲しいなと思います。
先ほど話した脱成長論、みたいなものですが、成功というのはただの目標であり結果で、過程にこそ真の財産があると思っています。そして「別にやめるのも自由だ」とも思います。もし、やめられないという思い込みがあるとすれば、それはきっと自分の脳味噌と社会が決めつけた固定観念です。心の赴くままに、自分だけに与えられる道を歩んで欲しいなと思います。

Joe Odagiri ●1976年生まれ、岡山県出身。アメリカと日本でメソッド演技法を学び、『アカルイミライ』(’03年)で映画初主演。以降、『メゾン・ド・ヒミコ』(’05年)、『ゆれる』(’06年)、『FOUJITA』(’15年)、『アジアの天使』(’21年)など、作家性や芸術性を重視した作品選びで独自のスタイルを確立。海外の映画人からの信頼も厚く、『悲夢』『Plastic City』(ともに’09年)、『マイウェイ』(’12年)、『宵闇真珠』(’18年)、『Saturday Fiction』(公開未定)などに出演。’19年に映画監督として初長編作『ある船頭の話』を手がけ、同作は第76回ヴェネチア国際映画祭・ヴェニス・デイズ部門に日本映画史上初選出。2021年度後期NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(2021年11月1日、総合あさ8時~放送開始)に出演。
Sosuke Ikematsu ● 1990年生まれ、福岡県出身。2003年『ラストサムライ』で映画デビュー以来、映画を主戦場に圧倒的な表現力で観客を魅了し、日本映画界には欠かせない存在に。主な出演作に映画『紙の月』『海を感じる時』『ぼくたちの家族』『愛の渦』(すべて’14年)、『劇場版MOZU』(’15年)、『セトウツミ』『デスノートLight up NEW world』(すべて’16年)、『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(’17年)、『斬、』『君が君で君だ』『万引き家族』(すべて’18年)、『町田くんの世界』『宮本から君へ』(ともに’19年)など。’21年は、中国映画『1921』と『柳川』が公開される(日本公開未定)。第93回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞、第41回ヨコハマ映画祭主演男優賞、2018年度全国映連賞男優賞、第9回TAMA映画賞最優秀男優賞ほか受賞歴多数。